
【この記事の著者について】
・現役の福祉施設職員
・2級FP技能士(2025年3月取得)
・2018年10月に株式投資をスタート!
・投資のスタイル:長期保有(バイアンドホールド)が基本
・高配当銘柄が大好き!株主優待も大好き!
・「社会福祉士が成年後見人を目指すブログ」を運営中
1. 福祉用具専門相談員の給料は本当に安い?
1-1. 平均給与と業界の実態
福祉用具専門相談員の平均年収はどのくらいなのか、気になる人も多いでしょう。業界全体の平均給与は決して高くはなく、特に経験が浅いうちは低収入に悩むことが多いのが現状です。また、地域や事業所の規模によっても大きな差があるため、自分の働く環境が給与水準にどう影響しているのかを知ることが重要です。
【福祉用具専門相談員の平均年収】
| 経験年数 | 平均年収 |
|---|---|
| 1~3年 | 約250万円 |
| 4~6年 | 約300万円 |
| 7年以上 | 約350万円以上 |
1-2. 給料が安い職場の特徴
【給料が安い職場の特徴】
- 小規模事業所で売上が不安定
- 賞与がない、昇給の機会が少ない
- 基本給が低く、手当がほとんどない
- 残業が多いのに手当が支給されない
福祉用具専門相談員の給与が低いと感じる理由の一つに、勤務する事業所の規模や経営状況があります。小規模事業所では売上が安定しづらく、給与水準が低めに設定されていることが多いです。また、賞与がない、昇給の機会が少ないといった点も、低収入の原因となります。一方で、大手企業では給与水準が比較的高く、福利厚生が充実しているケースが多いため、職場選びが収入に大きく関わってきます。
2. 福祉用具専門相談員が給料を上げる方法
2-1. 給料が高い職場を見つけるコツ
給料を上げるためには、まず給与水準の高い職場を見つけることが大切です。求人を探す際には、基本給のほかに手当や賞与の有無を確認し、年収ベースで考えることがポイントになります。また、大手企業は給与水準が高い傾向にありますが、営業ノルマや転勤の可能性なども考慮する必要があります。メーカー勤務であれば、直販営業などのポジションで高収入を狙える可能性があります。
2-2. 資格手当で収入アップ!取得すべき資格
【取得すべき資格と手当】
| 資格名 | 資格手当の目安 |
|---|---|
| 福祉住環境コーディネーター | 月5,000円~1万円 |
| 介護支援専門員(ケアマネ) | 月1万円~3万円 |
| 義肢装具士 | 高収入を狙いやすい |
福祉用具専門相談員の資格だけでは給与アップが難しい場合、追加で資格を取得するのも一つの手です。例えば、福祉住環境コーディネーターや介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格を持っていると、資格手当が支給されることがあり、収入アップにつながります。さらに、義肢装具士などの専門資格を取得すれば、より専門的な分野で高収入を目指すことも可能です。
2-3. 転職で年収アップを狙う方法
給与を上げるためには、転職を検討するのも有効な手段です。転職市場では、経験者が優遇されるケースが多く、特に営業力やコミュニケーション能力が高い人は、高収入のポジションに就くチャンスがあります。転職時には、過去の実績をしっかりアピールし、給与交渉を行うことが重要です。企業側に求められるスキルを把握し、それに合った経験を積むことで、転職による年収アップが期待できます。
3. 副業で収入を増やす!福祉用具専門相談員におすすめの副業
3-1. 福祉業界でできる副業
本業の知識や経験を活かして、副業を始めることで収入を増やすことが可能です。例えば、介護職の夜勤を週に1回入れるだけでも、月に数万円の収入アップが見込めます。また、福祉住環境コーディネーターとして、個人向けの住宅改修アドバイスを行うのも一つの方法です。研修講師やセミナー講師として活動することで、知識を生かしながら報酬を得ることもできます。
3-2. 異業種での副業で収入補填
福祉業界以外での副業を考える場合、ライティングやデータ入力などの在宅ワークが手軽に始められる仕事として人気です。特に、福祉関連の知識を活かした記事執筆は、専門性が評価されやすく、安定した収入につながる可能性があります。また、せどり(転売ビジネス)も、知識をつければ比較的簡単に収入を得られる方法の一つです。
3-3. 福祉用具専門相談員 × 副業の成功事例
【成功事例】
| 副業 | 収益化の方法 |
|---|---|
| ブログ運営 | アフィリエイト・広告収入 |
| YouTube | 福祉用具の使い方解説で収益化 |
| 個人販売 | 代理店ビジネスとして福祉用具を販売 |
福祉用具専門相談員としての知識を活かし、ブログやYouTubeで情報発信をすることで収益化を狙うこともできます。ブログでは、福祉用具のレビュー記事や転職情報を発信し、広告収入やアフィリエイト収益を得ることが可能です。YouTubeでは、福祉用具の使い方解説や介護現場のリアルな情報を発信することで、広告収益や企業案件を獲得できます。さらに、個人販売や代理店ビジネスとして、福祉用具を直接販売する方法も考えられます。
4. 独立・フリーランスという選択肢
4-1. 独立に必要な準備とスキル
独立を目指す場合、必要な資格や資金の準備が不可欠です。また、営業力も重要であり、顧客を獲得するスキルがなければ安定した収入を得るのは難しいでしょう。独立後の収益モデルとしては、福祉用具の販売やコンサルティング業務が挙げられます。
4-2. 介護保険外サービスでの収益化
介護保険適用外のサービスを提供することで、独自の収益モデルを構築することも可能です。例えば、高齢者向けの自費サービスとして、福祉用具の選定アドバイスや、住宅改修のコンサルティングを行うことで、収入を得ることができます。法人向けに福祉用具の選定支援を行うビジネスも、今後の可能性が期待されます。
5. まとめ:自分に合った収入アップ方法を選ぼう
福祉用具専門相談員の給料は決して高くはありませんが、転職、資格取得、副業などの方法を活用することで収入を増やすことは十分可能です。どの方法を選ぶかは、自分のスキルやライフスタイルに合わせて決めるのが良いでしょう。まずは、自分に合った収入アップの手段を見つけ、行動に移してみることが大切です。

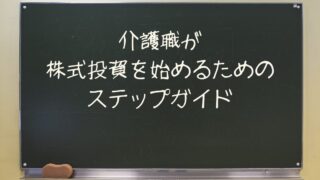


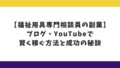

コメント