「ホームヘルパーの給料って、実際どれくらい手取りでもらえるの?」
そんな疑問を持って検索された方へ向けて、
実際の収入相場や手取り額、給料が安い理由、そして少しでも収入を増やすための方法まで、
根拠とともに詳しく解説します。
現場経験者にも納得いただけるよう、わかりやすい表や具体例も交えてお伝えします。

【この記事の著者について】
・現役の福祉施設職員
・2級FP技能士(2025年3月取得)
・2018年10月に株式投資をスタート!
・投資のスタイル:長期保有(バイアンドホールド)が基本
・高配当銘柄が大好き!株主優待も大好き!
・「社会福祉士が成年後見人を目指すブログ」を運営中
ホームヘルパーの給料と手取りの目安【2025年版】
ホームヘルパー(訪問介護員)の給料は、
働き方(常勤・非常勤)や地域、事業所の規模によって差があります。
以下は、厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」や各種求人サイトから得られるデータを基にした概算です。
| 勤務形態 | 月給(額面) | 手取り額(概算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 常勤(正社員) | 約21〜24万円 | 約17〜20万円 | 社会保険料や税金を差引いた後 |
| 非常勤(パート) | 時給1,200〜1,600円 | 月8万〜13万円(週3〜4日勤務想定) | 交通費支給や処遇改善手当含む |
※地域差や処遇改善加算の配分により、上記から上下することがあります。
ホームヘルパーの給料が「安い」と言われる理由
- 身体介護と生活援助で単価が違う
訪問介護は、身体介護(入浴・排泄・移動など)と生活援助(掃除・買い物など)で報酬単価が異なります。身体介護の方が高単価ですが、体力・スキルも求められ、利用者の状態によって件数が安定しません。 - 移動時間は「給料が出ない」ケースもある
訪問と訪問の間に発生する移動時間が無給だったり、報酬に含まれていなかったりする場合があります。 - パート勤務が多い業種
ホームヘルパーはパート勤務が主流であり、勤務時間が限られているため月収が伸びにくい傾向があります。
収入を増やすための方法
1. 介護福祉士の資格を取得する
介護福祉士を取得すると、処遇改善手当が増える・正社員登用されやすい・夜勤や他業務との兼務が可能になるなど、収入アップに直結します。
| 資格の有無 | 平均月収(概算) |
|---|---|
| 介護職員初任者研修のみ | 約21万円 |
| 介護福祉士 | 約26万円 |
(出典:厚生労働省 介護労働実態調査)
【参考になる記事があります!】
>>介護福祉士の初任給の手取りはいくら?給与の実態を徹底解説!
>>介護福祉士の手当を徹底比較!資格手当の平均額とは?施設による違いも解説
2. 訪問件数を増やす・シフトを増やす
時給制・件数制で働く場合、
1日の訪問件数を増やせばダイレクトに収入が上がります。
可能な範囲でシフトを増やすのも有効です。
3. 夜勤や他業種とのダブルワークを活用
訪問介護では日中勤務が基本のため、
夜勤ありのグループホームや有料老人ホームなどと掛け持ちすることで、収入の底上げができます。
【参考になる記事があります!】
>>夜勤専従×介護職におすすめの副業とは?収入アップの現実的な方法を解説
4. 副業・資格活用で収入の柱を増やす
副業OKの事業所も増えてきました。
以下のような副業がホームヘルパー経験者におすすめです。
- 介護ブログ・YouTubeでの情報発信
- 介護に関するライティング業務
- 家政婦・ベビーシッターなどのスポット業務
【参考になる記事があります!】
>>福祉業界で働く方へ!知識と経験を活かせるブログ副業のすすめ
実際の手取りが減る要因にも注意
- 社会保険料(厚生年金・健康保険)
- 住民税・所得税
- 自腹の移動費(交通費非支給の事業所もある)
- 処遇改善手当の支給タイミング(年2〜3回のボーナス型も)
これらの要因を含めて「思ったより手取りが少ない」と感じることも多いです。
求人票だけでなく、面接時に「支給実績」を必ず確認するのがポイントです。
まとめ:ホームヘルパーの給料・手取りの現実と未来
ホームヘルパーの仕事は尊く、社会的にも必要とされていますが、
給料面では厳しさもあります。
それでも、資格取得やスキルアップ、副業などを通じて収入アップの道は確実にあります。
手取りが少ない…それでも「誰かの役に立ちたい」と思える人こそ、長く働ける仕事です。
将来の安定や自分の生活のためにも、賢く働き方を選びましょう!

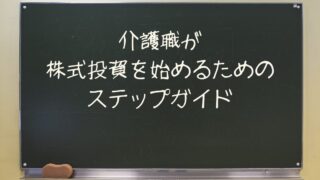




コメント