精神保健福祉士として働くうえで、給料だけでなく「ボーナスがどのくらいもらえるのか」気になる方も多いでしょう。本記事では、精神保健福祉士のボーナスの平均額や、高いボーナスが期待できる職場、さらにボーナスを増やす方法について詳しく解説します。

【この記事の著者について】
・現役の福祉施設職員
・2級FP技能士(2025年3月取得)
・2018年10月に株式投資をスタート!
・投資のスタイル:長期保有(バイアンドホールド)が基本
・高配当銘柄が大好き!株主優待も大好き!
・「社会福祉士が成年後見人を目指すブログ」を運営中
精神保健福祉士のボーナスはいくら?【平均額を解説】
精神保健福祉士の平均ボーナス額(全国データ)
精神保健福祉士のボーナスは、勤務先によって異なりますが、厚生労働省の統計データを参考にすると、年間平均で約3.5か月分の支給が一般的です。
具体的な金額でみると、
- 病院勤務(精神科病院など):年間50〜80万円程度
- 福祉施設勤務(障害者施設・相談支援事業所など):年間40〜70万円程度
- 自治体・公務員:年間70〜100万円以上
このように、勤務先によってボーナスの額に差があることが分かります。
公務員と民間のボーナスの違い
公務員(自治体勤務)の精神保健福祉士は、一般的に4.0〜4.5か月分のボーナスが支給されるため、比較的高めです。一方、民間の病院や福祉施設では、2.5〜3.5か月分が一般的で、施設によってはボーナスが支給されないケースもあります。
社会福祉士・介護福祉士と比較したボーナス額
他の福祉系資格と比べると、精神保健福祉士のボーナスは比較的高めの傾向があります。
- 精神保健福祉士:3.5か月分(50〜80万円)
- 社会福祉士:3.0か月分(40〜70万円)
- 介護福祉士:2.5か月分(30〜60万円)
これは、精神保健福祉士の専門性の高さや、病院勤務が多いことが影響していると考えられます。
精神保健福祉士のボーナスが高い職場・低い職場の特徴
ボーナスが高い職場の特徴(病院・行政機関・大手法人)
ボーナスが高い職場には以下の特徴があります。
- 精神科病院や公立病院:医療職として扱われるため、ボーナスの割合が高い
- 自治体・公務員:安定した給与体系で、ボーナス支給額が高め
- 大手社会福祉法人:経営が安定しており、ボーナスの支給が手厚い
ボーナスが低い職場の特徴(NPO・小規模事業所・委託業務)
反対に、ボーナスが少ない職場には以下のような傾向があります。
- 小規模の障害者支援事業所:財政基盤が弱く、ボーナスが出ないことも
- NPO法人や非営利団体:資金に余裕がなく、ボーナス支給が少ない
- 委託業務の相談支援員:ボーナスがなく、時給や月給制の報酬体系が多い
精神保健福祉士のボーナスを増やす方法
評価制度を理解し、昇給・昇格を狙う
病院や福祉施設では、昇格によってボーナスが増えるケースが多いため、評価制度をしっかり理解し、管理職やリーダー職を目指すことが重要です。
ボーナスが高い職場へ転職する
現在の職場でボーナスが少ない場合、より高いボーナスが期待できる職場へ転職するのも選択肢のひとつです。
- 病院(精神科・総合病院)
- 自治体の相談支援業務(公務員)
- 大手社会福祉法人の施設
転職サイトや求人情報を活用し、ボーナスがしっかり支給される職場を探すことが大切です。
副業で収入を補う(ブログ・講師・カウンセリングなど)
ボーナスを増やすのが難しい場合、副業で収入を補うのもおすすめです。
- ブログ運営:福祉業界の情報発信で広告収益を得る
- オンラインカウンセリング:精神保健福祉士の知識を活かした副業
- 講師業・セミナー開催:福祉業界向けの研修講師として活動
これらの副業を組み合わせることで、収入の柱を増やすことができます。
精神保健福祉士のボーナスが少ない場合の対策
ボーナスなしでも働きやすい職場の探し方
ボーナスがない職場でも、給与水準が高く、待遇が良い職場はあります。
- 月給が高い職場を選ぶ(ボーナスがなくても年収が安定する)
- 福利厚生が充実している職場を探す(住宅手当・資格手当など)
- 残業代がしっかり支給される職場を選ぶ
貯金や投資で収入を増やすコツ
ボーナスが少ない場合、貯金や投資を活用して資産形成するのも一つの方法です。
- 積立NISA・iDeCoで長期的な資産形成
- 固定費の見直し(通信費・保険など)で支出を削減
- 副業収入を投資に回す
このような工夫をすることで、収入の不安を減らすことができます。
まとめ|精神保健福祉士のボーナスを理解して賢く働こう
精神保健福祉士のボーナスは、勤務先によって大きな差があります。ボーナスが多い職場に転職する、昇格を狙う、副業を活用するなど、自分に合った方法で収入を増やしていくことが重要です。
この記事を参考に、自分のキャリアプランを考え、より良い働き方を目指しましょう。

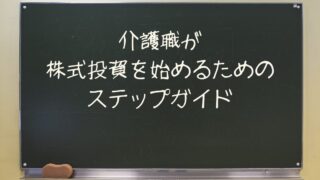




コメント